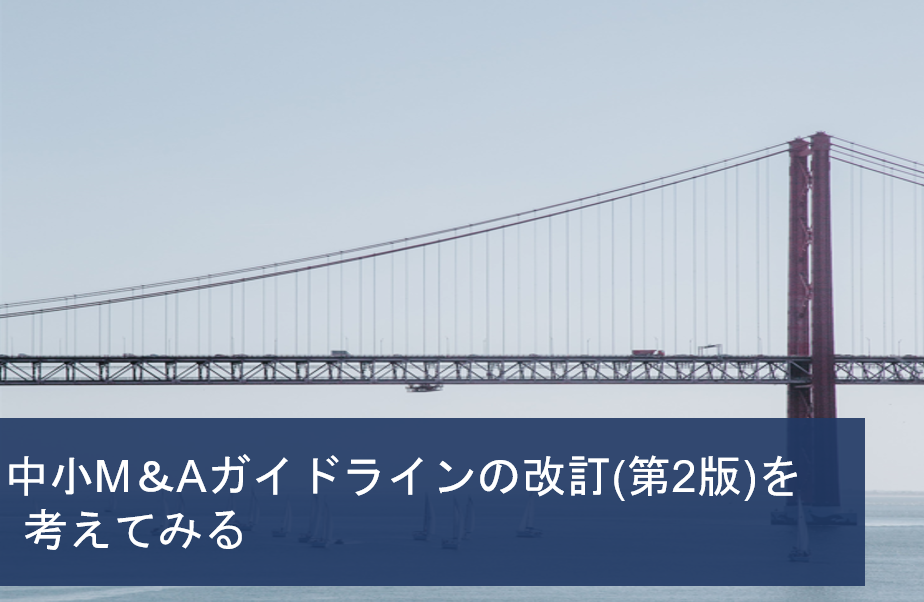
2023年9月22日に中小企業庁は「中小M&Aガイドライン(第2版)(*1)」を公表しました。これは3年前に公表された「中小M&Aガイドライン(初版)(*2)」の改訂版となります。前回のガイドラインが公表されて以降、中小M&Aの課題や特徴が一定程度整理され、中小M&Aも定着してきましたが、特段、参入障壁のないこの業界は、他業種や大手からの独立組等でM&A支援機関も大きく増加し、様々な問題が発生しています。そのためそれら問題に(一部)対応する形で、本ガイドラインが公表されました。
今回、大きく改訂された点は、以下の3点となります。
- ① 支援の質の確保・向上に向けた取組
- ・契約に基づく義務の履行・職業倫理の遵守の必要性の明記
- ・質の確保向上のため個々の支援機関・業界に求められる取組
- ②仲介契約・FA契約締結前の書面交付しての重要事項の説明
- ・書面に記載して説明すべき重要事項の項目の見直し
- ・説明の相手方・説明者・説明後の十分な検討時間の確保 等
- ③直接交渉の制限に関する条項の留意点
いずれも重要な論点で、これら論点が整理されたことは健全な業界を作っていく上で重要だと感じますが、一方で物足りなさも感じます。特に①については、やはりM&A業界には資格がなく業法もないため、アドバイザーとしての能力や倫理感を大きく底上げすることはできず、結局は会社や個々人に委ねざるを得ません。これでは大きく変わることはないでしょう。
中小M&A支援会社は、社員に大きなインセンティブを用意することで(つまり、目の前に人参をぶらさげることで)成長してきました。その結果が数年前に明らかとなった業界最大手の不正会計事件にもつながってきます(何十人もの社員が関与)。インセンティブ目的で働く社員ばかりの会社では、顧客の利益よりも自分の利益を守れればよいという社風になっていくのは当然です。
このような業界の環境下で中小企業庁が中小M&Aガイドラインを通じて業界の健全化を図っても、中大きな改善はなかなか見込めません。そこで資格や業法がない中で、中小M&A支援会社を牽制するためには、悪質なクレームや事件を中小企業庁が社名とともに開示することが効果的だと個人的に考えます。
(もしくはクレーム等の件数が多い中小M&A支援会社の上位3社とか5社を出すなど)
同じ会社が何件も開示されると顧客も依頼しなくなるので自然と淘汰されるはずです。直近でも、あるオーナーと話した際、大手仲介会社との仲介契約を何の説明もなく押印を迫られ(口頭で買い手の情報を話してしまったからとかいう理由で)、そんなもんかと押してしまった、という話も聞いたりもしています。こんな話も色々なところで出ているはずです。上記の案は極端な案かもしれませんが、やる必要が出てきたのではないでしょうか。
参考情報
(*1) 中小M&Aガイドライン(第2版)
(*2) 中小M&Aガイドライン(初版)
この記事の執筆者
- この記事の執筆者
- 公認会計士 門澤 慎